 |
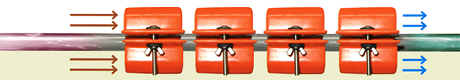 |
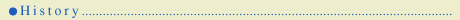 |
| 1200年 |
古代の航海の目標が太陽と星による観測であったものから、地球儀と共に磁気コンパスが北極星の方向を決めるための道具として使用された。 |
| 1600年 |
英国の物理学者ウイリアム・ギルバートは、磁石にはN極とS極があり、地球も磁石であるとした。地球の北極は巨大な地球磁石のN極と定義したが同意は得られなかった。 |
| 1825年 |
フランスの物理学者アンドレ・マリー・アンペールは、コイルに電気が流れるとNとSに分離した二つの極ができること、又右ネジの進む方向を電流、右ネジの回す方向が磁気線の向きに一致するなど発見した。 |
| 1831年 |
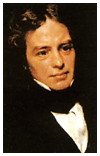 |
英国の物理学者であり科学者であるマイケル・ファラディーは、MHD理論の基礎となる磁気誘導電流を発見し、これが発電機の基礎原理となり「磁気の時代」が到来した。 |
| 1932年 |
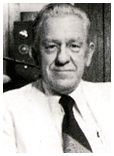 |
アメリカのアルバート・ロイ・デービス博士は、生物磁気の研究中に動植物に及ぼす効力をもとに磁石のプラスS極を発見し、この後、40年に及ぶ研究の成果は人間が健康を増進していく上の磁気の基礎原理となった。その後、虫・鼠等・細胞組織・水のN極とS極のエネルギーの違いを発見し 米国特許 ♯3947533を取得。 |
| 1950年 |
マイケル・ファラディーのMHD理論に基づき、旧ソ連・ヨーロッパでNS極MHDシステム(磁気活水装置)を開発。 |
|
|
 |
| |
|